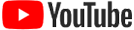小アラル海の国際協力について特別セミナーを開催しました。
- 2025/03/26
- お知らせ
乾燥地研究センターは、2025年3月19日に、2名の外国人研究者をオンラインで招へいして、「国際協力を通じたアラル海救済への努力~過去・現在・未来~」というテーマでの特別セミナーを開催しました。10名の学生、研究者、教員と一般の方が参加して、以下の発表が英語で行われました。
15:00 開会の辞 飯田 次郎(乾地研・准教授)及び地田徹朗(名古屋外国語大学・准教授、研究主幹)
15:10 基調講演 ニコライ・アラディン博士(ロシア科学アカデミー動物学研究所)
16:00 現地調査レポート 地田徹朗(名古屋外国語大学)
16:30 休憩
16:40 研究レポート 倉石東那(東京大学博士課程・日本学術振興会特別研究員 DC2)
17:10 マラト・ナルバエフ次長(アラル海救済国際基金カザフスタン事務所)
17:40 討議、質疑応答
開会の辞で、飯田准教授は、乾地研がアラル海保全に果たす役割とともに総合的な協力アプローチが有効であること、20年前と比較しカザフスタンは有言実行の国と実感しつつも、ソーシャルキャピタルは強化の余地が大きいことを指摘しました。地田准教授がセミナーの趣旨と出席者の略歴について説明した後に、ニコライ・アラディン博士からは、19世紀に遡るアラル海調査の歴史と、1980年から自身が関わってきた、45年間の経験が共有されるとともに、データ整備の重要性が強調され今後の展望についても示されました。地田准教授からは、2025年2月に小アラル海を一周して村落調査をした結果概要が紹介され、厳しい干ばつと水不足の中でも漁業や牧畜が営まれ、加工された水産物は欧州に輸出されている現状などが報告されました。倉石さんからは、国際河川シルダリア川に関連する国際協定の遵守に向けて、各国の取り組みの違いについて事例研究が示されました。IFASのナルバエフ次長からは、国際機関であるIFASの概要や成功した支援プロジェクトの紹介がなされ、シルダリア川の水管理、小アラル海の生態保全と住民の生計向上に果たしてきた成果が強調されました。
質疑応答では、アラル海の水位を維持する方法、水位が下がり住民が移住したことはあるか、干ばつが牧畜に与える影響、干ばつやゾドで失われた家畜の規模、食料安全保障とアラル海保全をいかに両立させていくべきか、上海協力機構との関連、近年の国際情勢がアラル海支援に与える影響などについて質問が出されました。また、アラル海保全には歴史学、生物学、水文学など総合的なアプローチが必要なこと、信頼や協力といったソフト面が重要であること、隣国と水をめぐる争い解決に向けた協力が必要なこと、地域経済振興がアラル海保全には有効なこと、乾地研との連携強化が必要なことなど、活発な意見交換が行われました。

小アラル海の現状について発表する地田准教授

ロシアやカザフスタンからの報告者を交えての集合写真